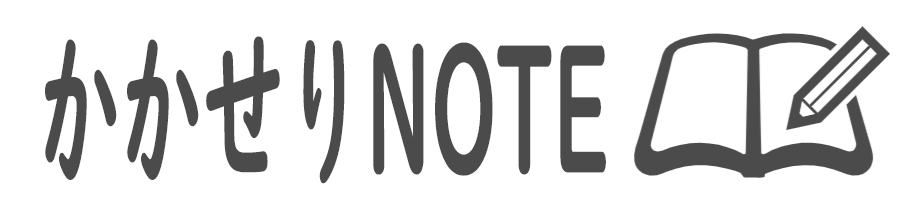・沢山売れている商品が利益を出しているのか、売上数量は少ないけど高額な商品が利益を出しているかわからない。
・いつもなんとなく、売上の高い商品ばかり見ていて売上の少ない商品の展開方法や販促を後回しにしている。
・利益を出している商品と利益を出していない商品を明確にしたいけどやり方がわからない。
そんな方の悩みを解決します。計算方法や実際の活用方法など、わかりやすく説明しますので是非読んで見てください。
交差比率(交叉比率)とは、利益が出てるかわかる計算式。


交差比率=商品回転率×荒利益率
上記の式で交差比率は表すことができます。
別名ではGMRO(グロス・マージン・リターン・オン・インベントリー)とも言いまます。
※GMROといっている人は見た事ありませんが・・・
店舗で勤務している際に交差比率を計算している人はあまりいないかもしれませんが今後あなたがステップアップしていくにつれて使うケースがあるかもしれませんし、だれかと話すときにもし交差比率の話が出てついていけたらきっと勉強しているな!と思ってもらえると思います。
商品回転率=売上高÷平均在庫金額で表すことが可能です。
交差比率(交叉比率)は何に使うのか。
交差比率は簡単に言うと、商品の収益性を見るときに使われています。
200%くらいの商品が収益性が高く効率よく稼いでいるラインと考えられています。
単純に交差比率に関しては収益性を確認するのに使うんだー。
200くらいあると収益性が高い商品なんだなーくらいに思っていれば良いんじゃないかなーと思います。
正直小売りで勤務していてもあまり使われているイメージはないですね。
※実際は使った方が良いとは思うので計算方法と使い方は絶対に覚えていた方が良いです。
交差比率(交叉比率)の計算方法
パターン1(荒利が低くて回転率が非常に高い商品のケース売れ筋の特売品などがこのケースになると思います)
| 荒利益率 | 商品回転率 | 交差比率 |
|---|---|---|
| 7% | 30回 | 210% |
パターン2(荒利はそこそこあって販売数もそこそこある商品ケース)
| 荒利益率 | 商品回転率 | 交差比率 |
|---|---|---|
| 20% | 20回 | 200% |
パターン3(荒利率が非常に高く販売数はあまり高くはない)
| 荒利益率 | 商品回転率 | 交差比率 |
|---|---|---|
| 60% | 3.3回 | 198% |
様々な商品が店舗にはあると思います。どれも収益性は変わらないですね。
パターン4(薄利で回転率も高くないケース)
| 荒利益率 | 商品回転率 | 交差比率 |
|---|---|---|
| 5% | 20回 | 100% |
上記は一見店舗ではそこそこ販売数があると思うかもしれませんが実際は収益性はあまり出ていない商品になります。
パターン5高荒利商品で販売数がほとんどなく商品回転率が上がらないケース
| 荒利益率 | 商品回転率 | 交差比率 |
|---|---|---|
| 60% | 2回 | 120% |
上記のような商品は感覚的に店舗もカットしたいなーと考えることはできるのではないでしょうか?
ここに関してはその感覚があっているから問題はないと思います。
ですが感覚で、判断してしまうと売れているからそのまま良い商品と思ってほっておくと、意図しないロスリーダーになっている可能性もあるのでたまに交差比率など活用して判断してみると良いのではないでしょうか?
※ロスリーダー:荒利を削って集客を狙うアイテム。
以上が簡単ですが交差比率の考え方になります。こんな計算式もあるんだなーくらいに覚えておくとよいかもしれません。
まとめ
交差比率は商品毎にどのくらいの利益を出しているか明確にすることができる指標になります。
ついつい、売上や数量ベースで商品を評価してしまうことが沢山あります。
ですが、小売業は利益を出さなくては顧客に還元することができないことも事実です。
沢山売れて、売上も稼いでくれる商品をついついもっと売りたいと思い沢山の販促経費をかけてチラシや各メディアに露出していくことが多くありますが、実際は交差比率が高い商品をよりメディアに露出して数量を高める方が効果的なケースも沢山あります。
今一度自分の担当している商品を1品ずつ交差比率を使って判断してみてはいかがでしょうか?
以下のイメージで表を作成すると良いかもしれません。
| 商品名 | 荒利率 | 商品回転率 | 交差比率 |
| バナナ | 5% | 20回 | 100% |
| みかん | 15% | 12回 | 180% |
| なし | 10% | 15回 | 150% |
| ぶどう | 20% | 8回 | 160% |
普段であれば、バナナが圧倒的に売れるからバナナが一番稼いでいる商品だと思いますが、実際に一番販売する必要があるのはみかんの可能性があります。
表にして交差比率のような数式を使うことで見えてくる事が沢山ありますので是非活用してみて下さい。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。